ヒューマンアカデミージュニアこどもプログラミング教室の評判は?
ヒューマンアカデミージュニアこどもプログラミング教室の評判は?
(PR)

全国600教室以上で開講している『ヒューマンアカデミージュニア こどもプログラミング教室』では、小学1年生からプログラミング学習をスタートできます。パソコンに触れるのが初めてというお子さまでも安心して通えるよう、段階的にスキルを身につけられるカリキュラムを用意。楽しみながら「考える力」を育てられる環境が整っています。
授業ではまず、簡単な課題を通じてパソコンの基本操作を学びます。そこから徐々にレベルアップし、自分でプログラムを改造・作成する力を育成。失敗を経験しながらも、試行錯誤を繰り返すことで、自分で考えて行動する「主体性」も養われます。
さらに、学びを楽しくするために開発されたオリジナル教材も魅力のひとつ。70種類以上のゲームやアニメーション、500以上のミッションが用意されており、子どもたちは遊び感覚で自然とスキルを身につけていきます。プログラミングを通して、未来につながるチカラを育てましょう。
詳細はこちら
ヒューマン アカデミー ジュニアこどもプログラミング教室の評判と料金

※こどもプログラミング教室の特徴
※子供のプログラミングスクール はやめとけ?
※プログラミングはやばい
※プログラミング教室の月謝・料金
こどもプログラミング教室の評判
ヒューマンアカデミージュニアこどもプログラミング教室は、全国に展開しているプログラミング教室の一つです。最近、子どもたちのプログラミング教育の重要性が高まる中で、多くの親がこの教室に注目しています。しかし、実際の評判はどうなのでしょうか。
口コミを調べると、まず良い点として多くの保護者が挙げるのは、子どもたちが楽しみながら学べる環境が整っていることです。ヒューマンアカデミーでは、ゲーム制作やロボット作りを通じて、子どもたちが自ら考え、問題を解決する力を育むことを目指しています。このような体験型の学習は、子どもの興味を引きやすく、学びを深める効果があります。
一方で、悪い評判もいくつか見受けられます。例えば、月謝がやや高めに設定されているため、経済的な負担を感じる家庭もあるようです。また、カリキュラムの内容が子どもによっては合わないと感じる場合もあります。特に、プログラミングに興味がない子どもには難しさを感じることがあるかもしれません。
総じて、ヒューマンアカデミージュニアこどもプログラミング教室は、楽しく学べる環境を提供し、多くの子どもたちに支持されていますが、個々のニーズに応じた選択が重要です。評判を参考にしつつ、子どもに最適なプログラミング教育を見つけることが大切です。
こどもプログラミング教室の特徴
こどもプログラミング教室は、小学生を対象にした「パソコンに触れることが初めてでも安心して学べる」教室です。全国に600教室以上あり、近くの教室に通える安心感も魅力のひとつです。この教室の大きな特徴は、子どもたちの「考える力」「やり抜く力」「楽しみながら学ぶ力」をバランスよく育てるカリキュラムにあります。
まず、授業はただ知識を教えるだけではなく、「どうすればうまくいくか?」を自分で考えながら取り組む内容になっています。たとえば、キャラクターを動かしたり、音を出す仕組みを作ったりと、実際にパソコンを操作しながら学ぶことで、自然と論理的な考え方や発想力が身につきます。
さらに、教材は子ども向けに作られたオリジナルの内容で、ゲームやアニメーションなどの楽しい要素がたくさん詰まっています。難しい言葉や操作は使わず、直感的に取り組めるため、飽きずに学び続けることができます。
また、子どもたち一人ひとりの成長に合わせて進められるので、「ついていけないかも…」という不安も不要です。初心者でも段階的に力をつけられるので、自信を持って通い続けられる教室として、多くの家庭に選ばれています。
子供のプログラミングスクール はやめとけ?
「子供のプログラミングスクールはやめとけ」というような声もあります。なので不安に感じる親御さんも多いかもしれません。このような声が出る理由には、「内容が難しすぎるのでは?」「ちゃんと続けられるの?」「費用が高い割に効果があるのか心配」といった疑問が関係しています。しかし、実際にはスクール選びを間違えなければ、多くのメリットが得られる学習の場です。
まず、最近の子供向けプログラミングスクールでは、専門用語を使わず、遊びの延長のような感覚で学べる教材が使われています。プログラミングというと「英語で書かれた難しいコード」を思い浮かべる方も多いですが、実際にはブロックを組み合わせて命令を作る“ビジュアル型”の学習が主流なので、小学生でも無理なく学べます。
「続けられるか不安」という点に関しても、最近のスクールでは子どもたちが達成感を味わえるよう、段階的に課題の難易度を上げたり、ゲームやアニメーションを作れるように工夫されています。これにより「もっとやりたい!」という気持ちが自然と芽生え、学習のモチベーションも維持しやすくなります。
ただし、どのスクールでも良いというわけではありません。大切なのは「子どもの興味や理解度に合ったカリキュラムが用意されているか」「サポート体制がしっかりしているか」を見極めること。体験授業などに参加して、子ども自身が楽しめるかどうかを確かめてから決めるのが失敗しないコツです。
プログラミングはやばい
「プログラミングはやばい」という言葉は、聞く人によって良い意味にも悪い意味にも受け取れます。ここでの「やばい」は、主に“すごい”“将来性がある”というポジティブな意味で使われることが多く、特に子どもが学ぶプログラミング教育においては、「やばい=とても役立つ」という見方が一般的になってきています。
まず、現代の社会ではスマートフォンやパソコン、ゲームなど、あらゆる場面でプログラミング技術が使われています。これからの時代、プログラミングは読み書きや計算と同じくらい大切な「基本的な力」として位置づけられていくといわれています。つまり、子どものうちからプログラミングに触れておくことは、将来の可能性を広げることにつながるのです。
また、プログラミングを学ぶことによって、単に「パソコンが使えるようになる」だけでなく、「問題を見つけて解決する力」や「論理的に考える力」「自分の考えを形にする力」など、将来さまざまな分野で役立つスキルが自然と身につきます。これは、どんな仕事に就くとしても、大きな武器になります。
もちろん、最初は難しく感じることもあるかもしれませんが、今の子ども向けプログラミング教材は、ゲーム感覚で楽しみながら学べるよう工夫されているので心配は不要です。「やばいくらい楽しい!」という声も多く、子どもたちが夢中になれる学びとして注目されています。
プログラミング教室の月謝・料金
子ども向けのプログラミング教室に通わせたいと思ったとき、やはり気になるのが月謝や初期費用などのお金の面ですよね。ここでは、ヒューマンアカデミージュニアの「こどもプログラミング教室」で用意されているコースごとの費用について、分かりやすく解説します。
この教室では、「ベーシック1」「ベーシック2」「ミドル」「アドバンス」と、成長に合わせてステップアップできる4つのコースが用意されています。すべてのコースで共通しているのは、月2回(1回90分)の授業があるという点です。そして、どのコースも月謝は10,560円(税込)となっています。1回あたり5,280円で、90分しっかりと学べることを考えると、比較的コストパフォーマンスが良いと言えるでしょう。
また、どのコースにも初期費用として13,420円(税込)が必要です。これは入会金や教材費などにあてられるもので、初めに一度だけ支払う費用です。学年やコースによってこの金額が変わることはありませんので、事前にしっかり準備しておきたいですね。
このように、月謝や費用は一見高く感じるかもしれませんが、内容の充実度や教材の質、個別サポートなどを含めて考えると、子どもの将来にとって有益な投資と言えます。無料体験もあるので、まずは実際に雰囲気を確かめてから検討してみるのもおすすめです。
詳細はこちら
小学生にプログラミング教室は本当におすすめ?
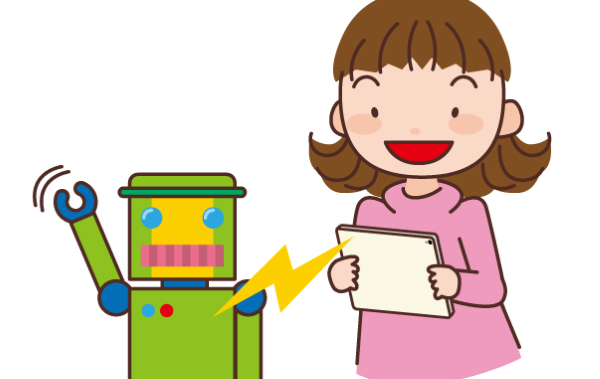
※子供のプログラミング教室は意味ない?
※子供は何歳からプログラミングを習わせる?
※子供の習い事ランキングでプログラミングは何位?
※ヒューマンアカデミージュニアロボット教室とは?
小学生にプログラミング教室はおすすめ
最近、「小学生にプログラミング教室って必要なの?」という声をよく耳にします。しかし実際には、今の時代だからこそ小学生からプログラミングを学ぶことがとても大切になっています。プログラミングは、ただパソコンでコードを書くというだけではなく、「自分で考えて行動する力」や「ものごとを順序立てて解決する力」を育てる
たとえば、子どもたちがゲームやアニメーションを作る体験を通して、「こうすればこう動く」という仕組みを自然と理解していきます。これは、遊びながら学べるので無理なく、しかも楽しんで続けることができます。さらに、「どうしたらもっと面白くなるかな?」と自分で考えるようになり、創造力や発想力もどんどん伸びていきます。
また、小学校でも2020年からプログラミング教育が必修化され、将来の社会ではコンピューターやITに関する知識が当たり前のように求められる時代になります。早いうちから慣れ親しんでおくことで、将来の選択肢もぐんと広がります。もちろん、将来エンジニアになるためだけでなく、どんな職業に就くとしても役立つ「考える力」を養えるのが魅力です。
プログラミング教室では、子ども一人ひとりのペースに合わせて学べるよう工夫されています。初心者でも安心してスタートできる環境が整っているので、「うちの子にできるかな?」と心配な方でも、まずは体験から気軽に始めてみるのがおすすめです。
子供のプログラミング教室は意味ない?
「子供のプログラミング教室は意味がないのでは?」と疑問に思う保護者の方もいるかもしれません。たしかに、「まだ小学生だし、プログラミングなんて早すぎるのでは?」「将来エンジニアになるとは限らないし…」と感じるのは自然なことです。でも、実はプログラミング教室は、ただ技術を教える場では
プログラミングとは、「こうしたい」という目的を持ち、それを実現するために順序立てて考え、工夫しながら形にしていく作業です。つまり、自分の頭で考えて試行錯誤する力が自然と身につくのです。これは将来どんな分野に進んでも役に立つ、非常に大切な力です。
また、多くの教室ではゲームづくりやアニメーションを通じて、楽しみながら学べるようになっています。子どもたちは遊び感覚で夢中になり、自分から学ぼうとする姿勢が育ちます。「意味がない」と言われることもありますが、実際には、子どもたちの好奇心や集中力、達成感を引き出す貴重な経験の場となっているのです。
もちろん、すべての子どもに合うとは限りませんが、体験授業などでまずは雰囲気を知ることができます。興味が湧いたときに始めてみるのがベストタイミングです。単にスキルを学ぶのではなく、「生きる力」を育てる場所として、プログラミング教室は大いに意味のある学び場だと言えるでしょう。
子供は何歳からプログラミングを習わせる?
「子どもにプログラミングを習わせるなら、何歳からがいいの?」という疑問は多くの保護者が抱くものです。実は、プログラミングは特定の年齢にならないとできないというものではなく、子どもの発達段階に合わせて、柔軟に始められるのが特徴です。最近では、
たとえば小学校1年生くらいになると、マウス操作や簡単な文字入力ができるようになり、プログラミングの基本的な操作にも対応できるようになります。教室によっては、ゲーム感覚で学べるビジュアルプログラミング(ブロックを組み合わせる方式)を採用しているため、読み書きが完全にできなくても楽しみながら学ぶことが可能です。
重要なのは「何歳から」よりも、「その子の興味関心がどれくらいあるか」「どんな学び方が合っているか」という点です。無理に早く始めるよりも、子どもが「やってみたい!」「面白そう!」と思ったタイミングで始めるのがベストです。まずは親子で体験教室に参加し、どんな内容かを一緒に見てみるのも良い方法です。
また、幼いうちからプログラミングに触れることで、論理的に考える習慣が自然と身についていきます。これは学校の勉強や日常生活の中でも役立つ力となります。「早すぎるかも」と心配するよりも、「楽しく始められる環境があるか」を重視して、子どもに合ったスタート時期を見つけてあげましょう。
子供の習い事ランキングでプログラミングは何位?
近年、子どもの習い事の中で「プログラミング」は急速に人気が高まっています。かつては水泳やピアノ、英会話といった習い事が定番でしたが、時代の変化とともに保護者の関心も変わりつつあります。実際のランキングを見ると、プログラミングはここ数年で着実に上位に食い込んでおり、特に小学生の男の子を中心に5位前後にランクインすることもあります。
その背景には、2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されたことが大きく影響しています。「学校で習うなら、早めに慣れておいた方が良いのでは?」という保護者の考えや、「将来の仕事に役立ちそう」という期待から、人気が高まっているのです。また、実際に通っている子どもたちからも「ゲームが作れるから楽しい」「自分で操作できるのが面白い」と好評です。
習い事ランキングでは、水泳や英語のように身体や語学を使う習い事も依然として根強い人気を誇っていますが、プログラミングは「将来役立つスキル」としての注目度が高く、今後さらに順位が上がることが予想されます。特にIT化が進む現代社会では、子どもたちにとってプログラミングは“新しい読み書きそろばん”のような存在になりつつあるのです。
もし「どの習い事を選べばよいか迷っている」という場合は、プログラミング教室の体験に参加してみるのがおすすめです。楽しみながら学べるかどうか、子どもの反応を見て判断することで、将来につながる良い選択ができるはずです。
ヒューマンアカデミージュニアロボット教室とは?
ヒューマンアカデミージュニアロボット教室は、全国に2,000教室以上展開し、これまでに10万人以上の子どもたちが通った実績のある人気のロボット教室です。47都道府県すべてに教室があるため、都市部だけでなく地方でも通いやすい点が魅力です。現在も在籍生徒数は27,000人以上と、多くの子どもたちが学んでいます。
この教室の教材は、日本を代表するロボット開発者・高橋智隆先生が監修しています。高橋先生は、しゃべるロボット電話「RoBoHoN(ロボホン)」や、宇宙で活躍した会話できるロボット「KIROBO(キロボ)」などを開発した第一人者です。そんな専門家が関わっていることで、教材の質の高さや実用性がしっかりと保証されています。
また、教室では年に数回、自分で作ったロボットを発表するイベントが行われており、子どもたちは自分の成長を実感する機会を持つことができます。ただ作るだけでなく、自分のアイデアを形にし、他人に伝える経験ができるため、表現力や自信も自然と身についていきます。
さらに、教室では5つの段階的なコースが用意されており、子どもの成長や興味に合わせてステップアップできる仕組みになっています。ロボット作りを通して、理科や数学といった理数系の力だけでなく、図形の見え方や組み立てのイメージ力など「空間認識能力」も育まれます。これはドリル学習では身につきにくい、実践的で貴重な能力です。
使用する教材も、オリジナルブロックとワークブックを組み合わせたもので、専門的な内容を無理なく体系的に学べるよう工夫されています。「学び=楽しい」と感じられる工夫がたくさん詰まった、まさに子どもの「知りたい」「やってみたい」を引き出す学びの場となっています。
詳細はこちら
運営者情報 お問い合わせ 特定商取引法に基づく表記
リンク集|1|2|3
